| ■経済とは |
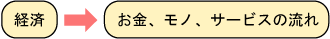 |
経済とはお金、モノ、サービスの流れのことです。モノを買うときには、売る人から買う人にモノが渡り、買う人から売る人にお金が渡ります。
モノがよく売れれば、お金の動きも活発になります。このような時期は「景気がよい」ことになります。一方、モノが売れず、お金の動きが鈍くなるときもあります。このような時期は「景気が悪い」ことになります。 |
| ■ニュースの言葉1 GDP |
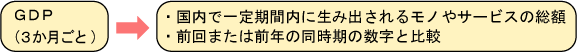 |
GDPとは、国内総生産(Gross Domestic Product)のことで、国内で一定期間内に生み出されたモノやサービスの価格の総額を示しています。GDPの大きさはその国の経済活動の実態を表しているとされ、1人当たりのGDPを国民ひとりひとりの豊かさをはかるモノサシの1つとすることもあります。
国の成長力を測るときには、一般にGDPの伸び率が使われます。日本など先進国のGDPの伸びは緩やかで、中国やインドなど新興国のGDPの伸びは大きいという傾向があります。 |
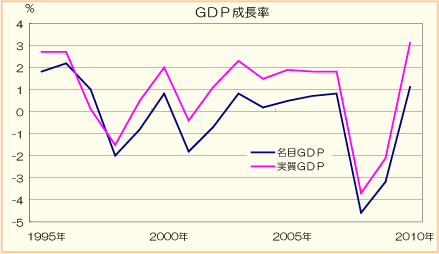 |
■景気がよいとは、どういうこと?
景気がよいということは、経済活動が活発であり、このような状態の時には一般に、モノが売れているということがいえます。モノが売れるのですから、通常、モノを作っている会社はもうかります。一般に会社の利益が増えれば、その一部は給与や賞与として従業員に分配されます。給与等が増えればモノを買う意欲が高まってモノが売れ、さらに景気がよくなるという好循環が生まれやすくなります。 |
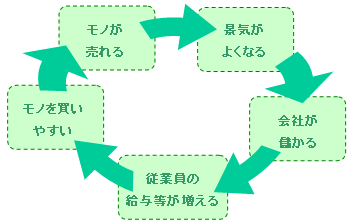 |
| 逆に、景気が悪いときにはモノが売れず、会社はもうからなくなり、従業員の給与・賞与は抑えられてしまいがちです(減ることもあります)。このようなときには、いわゆる「財布のヒモを絞める」ために、さらにモノが売れにくくなり、いっそう景気が悪くなるという悪循環に陥ってしまうことがあります。 |
■ニュースの言葉2 日銀短観
日銀短観とは、正式には、日本銀行が全国約1万社の企業を対象に実施している「全国企業短期経済観測調査」という、アンケート調査のことです。3か月に一度、将来の景気動向や企業経営などについて企業経営者にアンケートを行います。回収率もほぼ毎回99%程度と高く、信頼感があります。 |
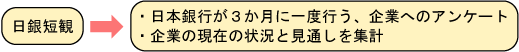 |
| なかでも、重視されているのは、大企業で製造業の企業が自社の業績を判断した回答(大企業製造業DI)です。「よい」「さほどよくない」「悪い」の答えのうち、「よい」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を差し引き、プラスならば現在の状況がよい、もしくは見通しが明るいということになります。 |
■物価
物価とは、モノの価格のことで、「食料品が値上がりした」というように身近で感じることのできるものです。景気がよいときは、少しくらい値段が高くてもモノが売れるので、物価は上がりやすく、景気が悪いときは、モノが売れにくいため、値下げをしてでもモノを売ろうとすることがあり、物価は下がりやすくなります。 |
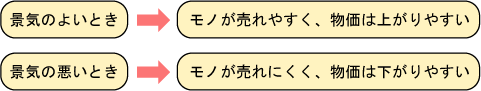 |
■ニュースの言葉3 インフレ・デフレ
インフレ(インフレーション)とは、物価が相当の期間にわたって持続的に上昇すること、またはお金の価値が持続的に低下することです。逆に、物価が持続的に低下する現象をデフレ(デフレーション)といいます。
景気が拡大すれば、物価が上昇することは自然な成行きです。インフレが緩やかに進み、給与が増えるならば、インフレによる悪い影響があったとしても、その影響は一時的なものになります。 |
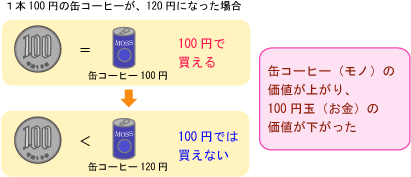 |
◆景気・物価と株式・金利
物価が急速に上がりそうなときには、政府はインフレにならないように金利を引き上げます。金利が上がれば、借金をしてまでモノを買う人が少なくなるため、モノの価格が上がりにくくなるという効果があるのです。
一方、景気が悪いときには、景気を回復させるために金利を引き下げます。お金が借りやすくなれば、個人は住宅などの大きな買い物をしやすくなりますし、企業は設備投資をしやすくなるからです。
また、景気がよいときは、会社の利益が増え、株式の価格(株価)が上昇しやすくなります。逆に、景気が悪いときは、会社の利益は増えず(減ることもあります)、株価は下落しやすくなります。 |
| 2012年6月現在 |
 暮らしと経済〜日本経済とニュースの言葉〜
暮らしと経済〜日本経済とニュースの言葉〜